【鼻めがね】・・・・・・・・・・・・よしとし 第2回
今回は"大相撲"のお話をします。太極拳なのになんで相撲!?なんて言わないで下さい。
実は"太極拳"の哲学的思想の柱になっている[陰陽・五行説]のお話しなんですから・・・。(注)長いお話になるので、2回にわけてお話します。
A:【広辞苑】によると、「相撲」は
"相撲・角力。「すま(争)ふ」(あらそう)から。土俵内で、二人が組み合い、力を闘わせて相手を倒すか、もしくは土俵外に出すことによって勝負を争う技。古代から宮廷で、相撲(すまい)の節として秋に行われた。"とあります。
また〔角力〕の角は比べる・せりあう・力比べするの意。
相撲は、古くは秋の取り入れの祭りとして行われていたのですね。現在でも、宮中の祭事には、このような中国文化の(暦、農事、ことに道教的)色合いの濃いものが伝えられています。例えば「新嘗祭:にいなめさい」のように。
B:次に行司さんの掛け声「ハッケヨイ」から。
"さあがんばれ!がんばって!"と言っているのでしょうが、もともとは中国語で「発起揚揚:faqi yangyang:ファチィヤンヤン」"意気揚々の盛んな様"を言ってるのだそうです。(日本相撲協会談)
C:次も行司さんの「・・・打ち止め―!」から。
その日、最後の取り組みであることを紹介するのに「本日はこの相撲一番にて・・・打ち止め―!」と声を上げます。私は"もうこれで拍子木を打つのを止めます"ということかなぁ?など思ったりしたことがありましたが、そうではありませんネ。
この打ち止めの「打:da」は日本語で"○○をする"とか、"ある手段・動作をとる"ことなど、広く使われています。
ところが、中国語では「打架:da jia=けんか。とっくみ合いをする」のように使っています。
ですから"太極拳をする=打太極拳:da tai ji quan"といいます。
したがって、「これで勝負は、取り組みは終わりですよ―!」ということですネ。
このように、相撲用語には、古く中国語がかかわっているのですネ―。
 | 写真1 |
かつて、土俵の四隅には、四本の丸太の柱が立ち、神明造の屋根を支えていましたが、今はつり屋根になりました。その柱のあった位置には、四つの色の大きな飾りの房が下がっています。
(1) [陰陽五行説]は、屋根の下に張り巡らされた水引幕を、四方それぞれの中央で絞り上げている揚巻(あげまき)の房の色にあります。
その揚巻は、青房、赤房、白房、黒房になっています。
これには、次のような意味があります。
◎ 青は東方をさし、守護神の青竜を、そして春を表しています。
◎ 赤(朱)は南をさし、朱雀(赤い鳥)を、そして夏を表します。
◎ 白は西方を指し、守護神の白竜を、そして秋を表します。
◎ 黒(玄)は北方を、玄武(黒い亀)を神とし、冬を表しています。
 | 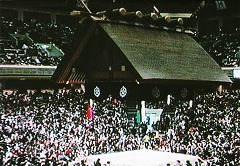 |
| 写真2 | 写真3 |
古墳のことなどで聞いたことのある名詞がたくさん出てきましたね。 ついでに玄武門(北方の門)・青竜寺・白虎隊・朱雀門(南方にある門)などなど・・・
連想してみてください。
あれ?勘の言い方はお気づきかもしれませんが、[陰陽・五行]というのに四行ではないか―?!
いえいえ、中央に黄色があるのですが・・・。この話しは次回に送りましょう。
(2) 水引幕は『水剋火:すいこくか』といい『火にかつ水』すなわち、土俵上の争う(すまう)熱気(火で陽の気)を紫色の幕(水で陰の気)によって鎮める。と言われています。陰・陽説ですね。
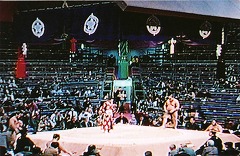 | 写真4 |
(3) 堅魚木(かつおぎ)の陰と陽にもふれましょう。
土俵の屋根の上に、円筒形の鰹節のような形が、棟木に直交するように、 何本か置かれていますね。
今の国技館では、五本で奇数:陽:男神を表して いるそうです。
では、六本のときは偶数:陰:女神ということになるのでしょう。
 | 写真5 |
力士は"東"と"西"から土俵に上がって、そして降りていきます。
南北とくに北(玄)が"正面"で南を"向う正面"と言い、正面に 審判長さんが座っていますね。
中国の都城の造営に当たっては、玉座を中心(黄色)にして 南北が軸になり、東西がその左右対称の配置になっています。
北京がそのいい例でしょう!
南北に行政府が、そしてその東と西の地区が一般民衆の居宅や市場が造られています。
なにしろ、中国語・で「買い物をする」は「買東西(mai dongxi)」という具合ですから。
皇帝が天を祭る天壇や、正陽門(真南の門)など、重要な建造物は、南北の軸の線上にあります。
韓国のソウルや、日本の京都などはどうなっているのでしょうか――?
ときに、「北まくらをするな!」と言うのを聞くことがあります。なぜ?
昔の陵の玄室は玄のとおり北にありますからね。
たぶんこんなところに源があるのでは・・・?
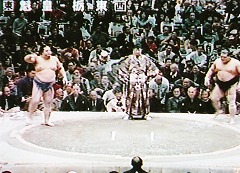 | 写真6 |
F、【塩撒き】という作法から
「なぜ塩を?」と聞くと、まず"土俵を浄める"という答えが返ってきます。
でも、料亭などで玄関に水を打って、入口の両脇に小さな白い"盛り塩"がしてあるのを目にしたことはありませんか?
これには、次のような中国の故事があるのです。
300年ごろ、西晋という国を建てた司馬炎という皇帝がいました。彼は風流人で自由人でもあったそうです。その後宮には、美女数百人を侍らしその部屋部屋を、数頭の羊が曳く車に乗って、夜毎巡回していくのだそうです。
そして、たまたまその羊車が停まったところの房を、その日の夜伽としたというのです。
そこで美女たちは、羊の足を停めるための考えをめぐらせました。
そして、羊の好きな"竹の葉に塩をそそいで部屋の通路に挿しかけた"そうです。
ですから、この故事を『挿竹灑塩(そうちくさいえん)』と言います。
つまり『幸せを招く塩』"招き塩"ですね。
相撲の"塩まき"は"勝ちを呼ぶ塩"と考えをめぐらせでみたらどうでしょうかネー。
G、『心』という字の手刀(てがたな)から
相撲は"礼に始まり、礼に終る"といわれます。 負けた力士が悔しさのあまりか時に礼をしないで土俵を下りると、審判長から注意されます。
また、勝った力士が、行司から懸賞金を受け取る時に手刀で『心』という字をなぞりながら受取っていますね。
[礼]の思想は、儒教思想のなかでも最も重要な道徳的観念です。礼をする。
心という字の手刀を切る。などは、その表現であり、いつの時代か作法として形になって伝えられてきたものでしょう。
剣道、柔道、茶道などにも、このようないろいろな「礼」の形(作法)がみられますね。
 |  |
| 写真7 | 写真8 |
第2回のまとめに
大相撲は『国技』といわれるように、古式に則った形が受け継がれているのが飾りなど。
このように、伝統にはそれぞれの持つ"様式"(形)が重んじられます。
そして、この様式また作法を守ることによって、普遍的な価値を持つ様式の美しさが生まれ、それが伝える力にもなっていくのでしょう。
また"ふるい"と言われながら、大相撲も、次々と新しい変革があっての現在であると思われます。
今回は、大相撲の形をとおして、実は、私たちの祖先が大陸の文化(陰陽・五行説、道教的祭礼儀式、易の科学、儒教的作法)を、自分たちのものにしていったか!
を振り返ってみました。

コメントする